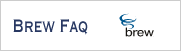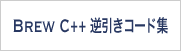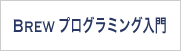2005 年 05 月 09 日 : Core concept -11-
最近のAUの携帯電話を利用されている方ならBREWというキーワードはご存知かもしれない。4月のKDDI発表によると、BREWが搭載された携帯電話普及台数が1000万台を突破したという。いまから3年前、私たちがBREWという新しきプラットフォームに着目し研究開発をスタートした時、国内マーケットにBREW搭載携帯電話はどこにも見当たらなかった。世界を見渡せば辛うじて、米国と韓国にそれらを合計しても数百万台というちっぽけなマーケットが存在するのみであった。
そしてBREWに関する研究開発に着手してから一年間というものは国内のBREWマーケットは文字通り"ゼロ"であった。しかも2003年から出荷が始まったBREW搭載携帯電話の出荷台数は伸び悩んだ。
そんな状況で、何故BREWを選択したかという意思決定の理由は、今後のソフィア・クレイドルの経営において極めて重要な要素と思われるので、今日はそのあたりの内容を簡単にまとめてみる。
モノが売れるには原因があるから結果としてそうなるわけで、その原因を創り出すことからベンチャー経営は始まるという風に考えた。モノが売れるということはそれを買う人がいるということである。モノ自体が機能や品質の面で他よりも優れているのは当然であるとしても、肝心の買う人はどこにいるのか?―――ということが最初の最大の課題であった。
マクロ的な視野から俯瞰すれば、日本の人口は”減少”の一途を辿っている。しかし、世界の人口は”爆発的に増加”しているという点に、着目すべきなのではないかと考えた。その事実から生じるシンプルな発想は、世界マーケットは拡大してゆくが国内マーケットは縮小の一途を辿る運命にある、ということである。おそらく今後数十年間はこの傾向が続くものと予測されよう。
ビジネスにおいて成功を収めるには、できるだけ長い期間に渡ってマーケットの伸びが期待できる方が良い。もしそうだとすると、仮に平凡な仕事をしていたとしても、上りのエスカレーターに乗るようにしてものごとは運ばれてゆくだろう。だからこそビジネスとして成立するかどうかの判断基準は、世界マーケットに持っていける製品を創れるか否かであった。そんな中にあって、BREWというプラットフォームは私たちにとって申し分の無いものであった。BREWは"情報通信"という国にとって商業的にも軍事的にも極めて重要なテクノロジーを提供する国策企業的な位置付けにあるUSのQualcomm, Inc.によるものなのだ。これが世界マーケットに拡がってゆくのは時間の問題と見なすことが出来た。
携帯電話だけでも数十億台ものポテンシャルがあるのに、私たちが始めた頃は、この広い世界マーケットには数百万台しかBREW搭載携帯電話は普及していなかった。何よりもスタッフがBREWというプラットフォームにテクニカルな興味を持ってくれたのが有り難かった。才能のあるスタッフが、興味や関心を持ち、熱意と情熱をもって研究開発に取り組めば、売れる資格の有る製品は必ず創れる。その時私はそう思った。
難しかった判断は、そのマーケットがいつからブレークするのか、そのタイミングであった。創業間もないベンチャーであるだけに、マーケットを動かすだけの体力は未だ無い。マーケットの変化の兆しをできるだけ早く察知し、それに向けた対応をするしかなかった。
通常の研究開発型ITベンチャーが創業時にするような受託案件もあまり受注せず、製品の研究開発に専念した。自らが主体となって自分たちの意志で100%自律的な経営をするというのが起業の理由でもあった。VC(ベンチャーキャピタル)などからの資金調達や銀行からの借り入れも創業以来ない。自社オリジナルのソフトウェアのライセンスを販売するビジネスなので仕入れもない。だから自己資本比率は100%に近く、経営には自由度と自律性がある。
ターゲットとすべきポイントは、数千万円かけてやる最初の研究開発投資をどういうタイミングで回収するかという一点に絞られた。研究開発だけをしているとお金も出てゆく一方なので、そのままだと何れ資金も枯渇し、倒産という憂き目を見ることに成りかねない。だから、研究開発をしつつその資金を得るために、スケールとしては、ソフィア・クレイドルの基幹製品よりは小粒なものも並行して研究開発し、その製品化と販売によって本命の製品の研究開発を支えた。
携帯電話の世界マーケットを考えた上で、製品寿命も長く、多くの人々に利用してもらえそうだと思ったプラットフォームがもう一つあった。それが携帯電話向けのJavaである。JavaはNTTドコモやボーダーフォンの携帯電話にも搭載され、3年前の2002年、既に数千万台ものマーケットが国内に実在していた。だから人々に必要とされ、売れる製品さえ創ればそこから収益を上げることは不可能では無かった。その時に閃いたのが、Javaのアプリケーションを圧縮するツールであった。携帯電話のアプリケーションにはサイズ制約があり、その問題をどうやってクリアすればよいかという点に、お客さまのニーズは確かに存在していた。
過去にこの日記にも記したように、このJavaアプリケーション圧縮ツールSophiaCompress(Java)の製品化と販売はさまざまな問題が発生したが、そんないくつかの壁をなんとか乗り越えて製品は売れるようになり、ソフィア・クレイドルの本命ともいえる基幹製品の研究開発を支えてくれた。最近では、SophiaCompress(Java)に対する海外からの問い合わせも増加の一途を辿り、今月ようやく海外対応版を出荷する予定である。
研究開発型ベンチャーの場合、初期の研究開発投資をどうやって賄うかという大きな難関が立ちはだかる。私たちは自由に好きなことを自分たちの意志で決めて実行することに重きを置いた。だから外部からの資金調達には最初から消極的なスタンスを取った。そしてそのためにはどうすれば良いかをじっくりと考えた。またできるだけ永続するようなスケール感のある企業へと育てたい夢と希望もあったので、常に世界的な視野からマーケットを眺める努力を欠かさなかった。
(つづく)